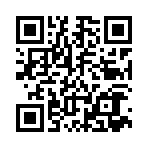2010年01月28日
Ⅳ.研究内容その2・・・
Ⅳ.研究内容その2(アンケート結果の把握・分析~長崎市との比較)
1.思わぬ落とし穴
上述のとおり29の自治体にアンケートをお願いしましたが、以下の理由から結果的には12の自治体の分については活用を断念せざるを得ませんでした。
1.協力いただけなかった自治体 → 4
2.実際の「ふるさと納税」実績が乖離していた自治体 → 8
上記2.については少しコメントする必要があります。
既に触れましたが、「個人からの都道府県・市区町村に対する寄附金調べ」は、「ふるさと納税」以外の個人寄附金も含んだ数値であるため、正確には同制度の実績とは異なります(長崎市の場合、同寄附金調べの実績は97件/5,402千円であるのに対して、「ふるさと納税」実績は48 件/2,694千円)。
しかし他に良いデータもないなかで、傾向として大きな齟齬はないだろうとの判断のもと、同寄附金調べを基に、先進自治体を抽出しました。ところが、8自治体については、何らかの理由(特定事業のために募集された寄附等と推察)により「ふるさと納税」以外の寄附がかなりの部分を占めていて、アンケートで改めて把握した実績は驚くほど僅少だったのです。
2.長崎市と17自治体との取組比較
アンケート項目毎に、特徴ある取組を行っている自治体とその概要について、長崎市での取組と比較する形でまとめたものが、次頁の【図表④】です。
(1)名称
殆どの自治体で特別の名称を設定していて、何れも各自治体の特色を表しています。
独断ですが、“がんばらんば長崎市”という名称の印象度は相当に高い方だと思います。
(2)使途目的
この項目は、「ふるさと納税」の最も特徴的なポイントですので、これをどう設定しているかを把握することが、今回アンケートの最も重要な目的とも言えます。私たちは、特に使途目的の幅広さと具体性の二点に着目してみました。
幅広さについては、各自治体ともに若干の違いはあれ、観光・地域振興から、自然等環境整備、教育、福祉といった市民生活に密着した項目まで、かなり幅広く担保していました。
長崎市の場合も、長崎市らしい平和推進や歴史を軸とした観光振興から、教育、福祉等の市民生活に身近なものまで幅広く設定されており、「寄附したいと思う項目が見当たらない」といった不満が出るような状況には思えません。
一方具体性については、【図表④】に挙げたように、いくつかの市町村で当該市町村出身者等が高い興味を持ってくれそうな個別具体的な使途目的を設定している例がありました。
長崎市の場合、平和推進、観光振興についてはかなり具体性が高いと思いますが、教育・子育て支援等に関しては、もう少し具体性を高める工夫が必要ではないでしょうか(【図表③】参照。)。
人づくりあってこそのまちづくりです。
行政の方で知恵がなければ、寄附者にアイディアを募るといった工夫があっても良いと思います。
また、そうした工夫が寄附者を増やすことにも繋がると考えます。

一つの面白い事例として茨城県阿見町の事例が挙げられます。
同町の使途目的は予科練平和記念館整備のみです。
同町は旧海軍飛行練習部いわゆる予科練が設置されていた所で、そのような歴史的な背景のなか同記念館の整備を進めることを目的に、平成19年度から同記念館整備管理基金を設置して寄附を募ってきた経緯があり、「ふるさと納税」についても同目的のみに限定しているとのことでした。
阿見町のこの事例は、「ふるさと納税」の今後の発展を考えるうえで一つの貴重な示唆かもしれません。
(3)PR・周知
PRや周知は、実績を上げるために極めて重要な取り組みです。
特に、大票田とも言うべき東京等大都市圏に住む長崎市出身者や長崎市に縁のある方々への働きかけが、大きなポイントを握っています。
長崎市でも実施しているHPや市報等での紹介、リーフレットやポスター等の作成、高校同窓会等でのPRは、いずれの自治体でも実施している三点セットのようです。しかしながら、こうした取り組みは多数を相手にしたマスコミ的手法であり、実際に行動を起こしてもらおうと働きかけるという観点からは、淡泊な印象は否めません。
私たちは、的を絞ったダイレクトメール的な方法はないものかと考えてみました。例えば、滝上町の「ふるさと通信」は面白い事例だと思いますが、長崎市の規模ではちょっと難しい施策です。費用対効果を考えると、そう多くのお金もかけらませんし、個人情報保護が厳しい昨今、個人データを集めるのもかなりの苦労です。
そこで私たちが考えついたのが、市役所から長崎市内家庭にダイレクトに年賀状を送り、「ふるさと納税」をお願いするという方法です。
年末年始であれば多くの方々が帰省しており、普段は長崎市を離れて住んでいる方の目に触れる可能性大です。
デザイン等に工夫を凝らすこと(例えば、福山雅治さんに登場して頂く)で、強烈な印象を与えることもできます。さらに、一人立ちしている子弟を持つ可能性の高い年齢層、例えば世帯主が50才以上の家庭に絞って郵送すれば、費用の節約も可能です。
また、少し視点の異なる仕組みを採用している事例を紹介したいと思います。
自治体間の税源の取り合いのなかで、鹿児島県では、県と市が一体となった取組を実施しています。具体的には、県単位で「ふるさと納税」窓口を一本化し、寄せられた金額総額については、
1.県への配分:市町村トータルへの配分=4:6
2.市町村トータル分の各市町村への配分については、寄附者の指定を基本に決定
という内容です。
ややもすれば県と市町村で重複した活動となりがちであるなかで、こうした方法は効率的であり、また納税者の立場からしても判り易い取組と言えそうです。
(4)特典付与
半数以上の自治体が、特産品や自治体内施設利用優待券等を送付しています。現実的にはこの辺りの工夫が納税獲得実績を左右しているということもあるでしょう。
こうした「物で釣る」方式には賛否両論あるかと思います。「背に腹は代えられない」と考えれば、こういう方法があることを決して否定はしませんが、私たちは“質実剛健、中身で勝負”の長崎市のやり方に全面的に賛同します。皆さんはどうでしょうか。
そうしたなかで、阿見町の予科練平和記念館芳名版設置や、長野県飯山市の新幹線駅関連施設刻銘は、使途目的と絡めた面白い事例だと思います。
(5)利便性向上
東京で生活している者の立場からすると、三大メガバンクでの振込やクレジットカード使用が可能であることは、利便性の観点からありがたい施策です。特にクレジットカードでの支払いを現状で導入している自治体はそう多くありませんが、長崎市では平成21年より早速導入しており、迅速な対応として評価できると思います。
一部金融機関での振込手数料を市町村が負担している事例も複数見られました。
金額的な負担軽減はわずかですが、納税という観点からは無料が当然だというのが寄附者の率直な感情だと思います。
長崎市の場合も全国規模で利用できる金融機関としては、ゆうちょ銀行とみずほ銀行について、振込手数料が自治体負担となっていますが、これをさらに三大メガバンク等にも拡大することを期待します。
(6)フィードバック
「税の使いみちが見える」ことが「ふるさと納税」制度の大きな特色ですので、実績のフィードバックは、使途目的の設定とコラボレーションした重要な施策と考えます。
しかしながら現状においては制度を導入して間もないこともあり、長崎市も含めて寄附実績の送付やHPでの公開というマスコミ的手法の域を出ていません。
今後は、使途目的として設定された個別事業の具体的な進捗状況をタイムリーにフィードバックすることなどが必要ではないでしょうか。
また、そうしたフィードバックにおいては、無味乾燥な文章のみによるものではなく、ビジュアルであったり、当該事業で恩恵を受けた方々の生の声を紹介したりといった、寄附された方を心地よくしリピーターとして取り込むぐらいの意気込みの感じられる工夫を織り込んでほしいと思います。
1.思わぬ落とし穴
上述のとおり29の自治体にアンケートをお願いしましたが、以下の理由から結果的には12の自治体の分については活用を断念せざるを得ませんでした。
1.協力いただけなかった自治体 → 4
2.実際の「ふるさと納税」実績が乖離していた自治体 → 8
上記2.については少しコメントする必要があります。
既に触れましたが、「個人からの都道府県・市区町村に対する寄附金調べ」は、「ふるさと納税」以外の個人寄附金も含んだ数値であるため、正確には同制度の実績とは異なります(長崎市の場合、同寄附金調べの実績は97件/5,402千円であるのに対して、「ふるさと納税」実績は48 件/2,694千円)。
しかし他に良いデータもないなかで、傾向として大きな齟齬はないだろうとの判断のもと、同寄附金調べを基に、先進自治体を抽出しました。ところが、8自治体については、何らかの理由(特定事業のために募集された寄附等と推察)により「ふるさと納税」以外の寄附がかなりの部分を占めていて、アンケートで改めて把握した実績は驚くほど僅少だったのです。
2.長崎市と17自治体との取組比較
アンケート項目毎に、特徴ある取組を行っている自治体とその概要について、長崎市での取組と比較する形でまとめたものが、次頁の【図表④】です。
(1)名称
殆どの自治体で特別の名称を設定していて、何れも各自治体の特色を表しています。
独断ですが、“がんばらんば長崎市”という名称の印象度は相当に高い方だと思います。
(2)使途目的
この項目は、「ふるさと納税」の最も特徴的なポイントですので、これをどう設定しているかを把握することが、今回アンケートの最も重要な目的とも言えます。私たちは、特に使途目的の幅広さと具体性の二点に着目してみました。
幅広さについては、各自治体ともに若干の違いはあれ、観光・地域振興から、自然等環境整備、教育、福祉といった市民生活に密着した項目まで、かなり幅広く担保していました。
長崎市の場合も、長崎市らしい平和推進や歴史を軸とした観光振興から、教育、福祉等の市民生活に身近なものまで幅広く設定されており、「寄附したいと思う項目が見当たらない」といった不満が出るような状況には思えません。
一方具体性については、【図表④】に挙げたように、いくつかの市町村で当該市町村出身者等が高い興味を持ってくれそうな個別具体的な使途目的を設定している例がありました。
長崎市の場合、平和推進、観光振興についてはかなり具体性が高いと思いますが、教育・子育て支援等に関しては、もう少し具体性を高める工夫が必要ではないでしょうか(【図表③】参照。)。
人づくりあってこそのまちづくりです。
行政の方で知恵がなければ、寄附者にアイディアを募るといった工夫があっても良いと思います。
また、そうした工夫が寄附者を増やすことにも繋がると考えます。

一つの面白い事例として茨城県阿見町の事例が挙げられます。
同町の使途目的は予科練平和記念館整備のみです。
同町は旧海軍飛行練習部いわゆる予科練が設置されていた所で、そのような歴史的な背景のなか同記念館の整備を進めることを目的に、平成19年度から同記念館整備管理基金を設置して寄附を募ってきた経緯があり、「ふるさと納税」についても同目的のみに限定しているとのことでした。
阿見町のこの事例は、「ふるさと納税」の今後の発展を考えるうえで一つの貴重な示唆かもしれません。
(3)PR・周知
PRや周知は、実績を上げるために極めて重要な取り組みです。
特に、大票田とも言うべき東京等大都市圏に住む長崎市出身者や長崎市に縁のある方々への働きかけが、大きなポイントを握っています。
長崎市でも実施しているHPや市報等での紹介、リーフレットやポスター等の作成、高校同窓会等でのPRは、いずれの自治体でも実施している三点セットのようです。しかしながら、こうした取り組みは多数を相手にしたマスコミ的手法であり、実際に行動を起こしてもらおうと働きかけるという観点からは、淡泊な印象は否めません。
私たちは、的を絞ったダイレクトメール的な方法はないものかと考えてみました。例えば、滝上町の「ふるさと通信」は面白い事例だと思いますが、長崎市の規模ではちょっと難しい施策です。費用対効果を考えると、そう多くのお金もかけらませんし、個人情報保護が厳しい昨今、個人データを集めるのもかなりの苦労です。
そこで私たちが考えついたのが、市役所から長崎市内家庭にダイレクトに年賀状を送り、「ふるさと納税」をお願いするという方法です。
年末年始であれば多くの方々が帰省しており、普段は長崎市を離れて住んでいる方の目に触れる可能性大です。
デザイン等に工夫を凝らすこと(例えば、福山雅治さんに登場して頂く)で、強烈な印象を与えることもできます。さらに、一人立ちしている子弟を持つ可能性の高い年齢層、例えば世帯主が50才以上の家庭に絞って郵送すれば、費用の節約も可能です。
また、少し視点の異なる仕組みを採用している事例を紹介したいと思います。
自治体間の税源の取り合いのなかで、鹿児島県では、県と市が一体となった取組を実施しています。具体的には、県単位で「ふるさと納税」窓口を一本化し、寄せられた金額総額については、
1.県への配分:市町村トータルへの配分=4:6
2.市町村トータル分の各市町村への配分については、寄附者の指定を基本に決定
という内容です。
ややもすれば県と市町村で重複した活動となりがちであるなかで、こうした方法は効率的であり、また納税者の立場からしても判り易い取組と言えそうです。
(4)特典付与
半数以上の自治体が、特産品や自治体内施設利用優待券等を送付しています。現実的にはこの辺りの工夫が納税獲得実績を左右しているということもあるでしょう。
こうした「物で釣る」方式には賛否両論あるかと思います。「背に腹は代えられない」と考えれば、こういう方法があることを決して否定はしませんが、私たちは“質実剛健、中身で勝負”の長崎市のやり方に全面的に賛同します。皆さんはどうでしょうか。
そうしたなかで、阿見町の予科練平和記念館芳名版設置や、長野県飯山市の新幹線駅関連施設刻銘は、使途目的と絡めた面白い事例だと思います。
(5)利便性向上
東京で生活している者の立場からすると、三大メガバンクでの振込やクレジットカード使用が可能であることは、利便性の観点からありがたい施策です。特にクレジットカードでの支払いを現状で導入している自治体はそう多くありませんが、長崎市では平成21年より早速導入しており、迅速な対応として評価できると思います。
一部金融機関での振込手数料を市町村が負担している事例も複数見られました。
金額的な負担軽減はわずかですが、納税という観点からは無料が当然だというのが寄附者の率直な感情だと思います。
長崎市の場合も全国規模で利用できる金融機関としては、ゆうちょ銀行とみずほ銀行について、振込手数料が自治体負担となっていますが、これをさらに三大メガバンク等にも拡大することを期待します。
(6)フィードバック
「税の使いみちが見える」ことが「ふるさと納税」制度の大きな特色ですので、実績のフィードバックは、使途目的の設定とコラボレーションした重要な施策と考えます。
しかしながら現状においては制度を導入して間もないこともあり、長崎市も含めて寄附実績の送付やHPでの公開というマスコミ的手法の域を出ていません。
今後は、使途目的として設定された個別事業の具体的な進捗状況をタイムリーにフィードバックすることなどが必要ではないでしょうか。
また、そうしたフィードバックにおいては、無味乾燥な文章のみによるものではなく、ビジュアルであったり、当該事業で恩恵を受けた方々の生の声を紹介したりといった、寄附された方を心地よくしリピーターとして取り込むぐらいの意気込みの感じられる工夫を織り込んでほしいと思います。
Posted by 在京長崎応援団塾 at 03:05│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。